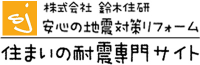耐震コラム
耐震診断不要でも安心できる家づくり・耐震性の確保方法

地震はいつ起こるか分かりません。
大切な家族を守るため、住まいの耐震性をしっかり確認しておきたいですよね。
でも、「耐震診断って必要なの」「費用はどれくらいかかるの」と不安に思う方もいるのではないでしょうか。
実は、新耐震基準を満たす住宅を建てることで、耐震診断が不要になる可能性があります。
今回は、西東京市・小平市・東久留米市周辺で耐震補強をお考えの方に向けて、耐震診断不要でも安心できる家づくり、耐震性の確保方法についてご紹介します。
新耐震基準を満たす家づくりで耐震診断不要を目指す
新耐震基準とは何か
新耐震基準とは、1981年(昭和56年)6月1日に改正された建築基準法に基づく耐震基準のことです。
それ以前の基準(旧耐震基準)では、震度5強程度の地震に対して倒壊しないことを目標としていましたが、1978年の宮城県沖地震で多くの建物が被害を受けたことを受け、基準が大幅に見直されました。
新耐震基準では、より大きな地震に対しても倒壊しないよう、建物の構造や設計が厳しく規定されています。
具体的には、建物の壁量を増やす、接合部の強度を高めるなどの対策が盛り込まれています。
木造住宅に関しては、2000年(平成12年)にも基準が改正され、さらに耐震性が向上しています。
新耐震基準に適合した住宅を建てる方法
新耐震基準に適合した住宅を建てるには、建築士などの専門家に設計を依頼することが重要です。
設計段階で新耐震基準を満たすための構造計算を行い、適切な材料を選択することで、安全な住宅を建てることができます。
また、建築確認申請を必ず行い、行政機関による検査を受けて合格することが必要です。
これは、建築基準法で定められた手続きであり、新耐震基準への適合性を確認するための重要なステップです。
設計図書をきちんと作成し、建築確認申請の際に提出することで、スムーズな建築確認が期待できます。
新築時における耐震性を高める工夫
新耐震基準を満たすだけでなく、さらに耐震性を高める工夫も可能です。
例えば、制震ダンパーや免震装置などを導入することで、地震による揺れを軽減することができます。
これらの装置は、地震のエネルギーを吸収したり、建物の揺れを抑制したりする役割を果たします。
また、建物の基礎をしっかりとしたものにする、耐震性に優れた木材を使用するなども効果的です。
地盤調査をしっかりと行い、地盤の状況に合わせた基礎設計を行うことも、非常に重要です。
さらに、耐震性を高めるための適切な補強方法を建築士と相談することも有効です。
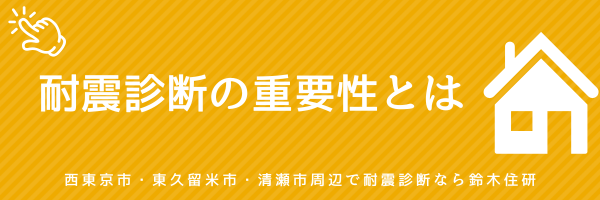
耐震診断不要でも安心できる住宅のポイント
建築時の確認事項
住宅を建てる際には、設計図書を丁寧に確認し、新耐震基準への適合性をしっかり確認しましょう。
設計図書には、建物の構造、使用する材料、そして耐震計算の結果などが記載されています。
専門用語が分からなければ、建築士に丁寧に説明してもらいましょう。
また、建築工事の過程で、設計図書通りに工事が進められているかを定期的に確認することも大切です。
適切な建築材料の選定
耐震性が高い建築材料を選択することも重要です。
例えば、木材であれば、乾燥が十分に行われ、強度の高い木材を選びましょう。
また、接合部には、耐震性に優れた金物を使用することが効果的です。
コンクリートや鉄骨などの材料を使用する場合は、品質の高い材料を使用し、適切な施工を行う必要があります。
定期的な点検とメンテナンス
建物が完成した後も、定期的な点検とメンテナンスを行うことは重要です。
地震による被害がないかを確認し、必要に応じて修繕を行うことで、建物の寿命を延ばし、安全性を維持することができます。
専門業者による点検を定期的に行うことをおすすめします。
小さな不具合を見逃さず、早期に対応することで、大きな被害を防ぐことができます。
まとめ
耐震診断は、既存の建物の耐震性を確認するためのものです。
しかし、新耐震基準を満たすように設計・施工された新築住宅であれば、耐震診断は必ずしも不要とは言い切れませんが、必要ないケースが多いでしょう。
今回は、新耐震基準を満たす家づくり、そして耐震診断不要でも安心できる住宅のポイントについて解説しました。
安全で安心できる住まいを手に入れるためには、設計段階からの丁寧な確認と、建築後も継続的なメンテナンスが不可欠です。
投稿者プロフィール
- 「鈴木住研」では、これまでに300棟以上の木造住宅の耐震診断を行ってきました。
経験豊富な東京都登録の耐震診断技術者(建築士)が責任を持って耐震診断を行なっております。
また、創業より60余年木造住宅を造り続けてきた工務店の高い技術力・施工力で、精度の高い、補強工事も行なっております。
アフターメンテナンスを欠かさず、社員や協力会社と共に、お客様のご家族と住まいを長期にわたり見守り続けます。
ぜひ安心して相談ください。