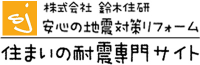耐震コラム
昭和56年の築物件の耐震診断は必要?安心安全な家選びのための知識

昭和56年築の物件、購入を検討されている方も多いのではないでしょうか。
築年数が古くても魅力的な物件はたくさんあります。
しかし、昭和56年は耐震基準が大きく変わった年。
気になるのは耐震性ですよね。
今回は、西東京市・小平市・東久留米市周辺で耐震補強をお考えの方に向けて、昭和56年を境にした耐震基準の違いを分かりやすく解説し、昭和56年築物件の耐震診断の重要性、診断を受ける際のポイントをご紹介します。
昭和56年問題と耐震基準の違いを知ろう
旧耐震基準と新耐震基準・その違いとは何か
1981年(昭和56年)6月1日、建築基準法が改正され、耐震基準が大きく変更されました。
それ以前の基準を「旧耐震基準」、改正後の基準を「新耐震基準」と呼びます。
旧耐震基準は、震度5強程度の地震を想定していましたが、阪神・淡路大震災や東日本大震災などの経験から、その耐震性が不十分であることが明らかになりました。
新耐震基準では、震度6強~7程度の地震にも耐えられるよう、建物の構造や設計が強化されています。
具体的には、建物の骨組みとなる柱や梁の強度、接合部の耐力などが向上しました。
旧耐震基準で建てられた建物は、地震によって倒壊するリスクが高いとされています。
昭和56年以前の建物と耐震性・地震リスクの現状
昭和56年以前に建築された建物は、旧耐震基準で建てられている可能性が高いです。
もちろん、昭和56年以前に建築確認申請が受理された建物でも、新耐震基準に準拠して建築された建物も存在します。
しかし、建築確認申請書や図面、構造計算書などを確認しなければ、実際に新耐震基準が適用されているかどうかは判断できません。
これらの書類は、建築後、一定期間経過すると紛失している場合も多いです。
そのため、昭和56年以前の建物は、耐震性が不十分であると判断し、地震に対するリスクを高く評価することが一般的です。
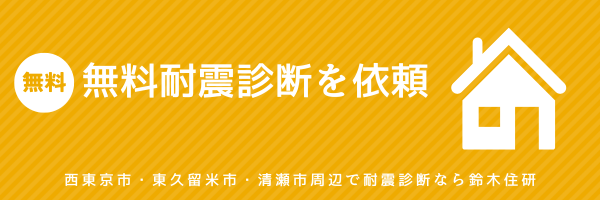
耐震診断 昭和56年築物件のチェックポイント
耐震診断の必要性と費用・自治体の補助金制度
昭和56年築の物件を購入する際には、耐震診断の実施が強く推奨されます。
耐震診断は、専門家が建物の耐震性を調査し、地震に対する強さを評価するものです。
診断の結果、耐震性に問題がある場合は、補強工事が必要となる可能性があります。
耐震診断の費用は、建物の規模や構造によって異なりますが、数十万円から数百万円かかる場合もあります。
しかし、多くの自治体では、耐震診断や耐震補強工事に対する補助金制度を設けています。
自治体によって制度の内容は異なりますので、お住まいの地域の窓口に問い合わせて、詳細を確認することをお勧めします。
耐震診断の結果と今後の対応・補強工事の検討
耐震診断の結果は、建物の耐震性を評価する指標である「構造耐震指標(Is値)」で示されます。
Is値が基準値を下回ると、耐震補強が必要と判断されます。
補強工事には、様々な方法があり、建物の構造や損傷状況、予算などを考慮して最適な方法を選択する必要があります。
補強工事の費用は、診断結果や工事内容によって大きく変動します。
補強工事を行う場合、専門業者に依頼することが重要です。
信頼できる業者を選ぶため、専門業者に依頼することをお勧めします。
また、工事の内容や費用について、十分に理解した上で契約を結びましょう。
昭和56年築物件の購入を検討する際の注意点
昭和56年築物件を購入する際には、耐震性の問題以外にも注意すべき点があります。
例えば、建物の老朽化による修繕費用、設備の更新費用などです。
築年数が古い物件ほど、これらの費用が高くなる可能性があります。
物件選びの際には、これらの費用についても考慮し、予算に見合った物件を選ぶことが重要です。
また、物件周辺の環境、交通アクセス、生活利便性なども考慮し、総合的に判断しましょう。
まとめ
昭和56年を境に耐震基準が大きく変わったことは、中古住宅選びにおいて非常に重要なポイントです。
昭和56年築の物件は、旧耐震基準で建てられている可能性が高く、地震に対するリスクが高いと認識しておくべきです。
そのため、購入を検討する際には、必ず耐震診断を実施し、建物の耐震性を確認することが大切です。
投稿者プロフィール
- 「鈴木住研」では、これまでに300棟以上の木造住宅の耐震診断を行ってきました。
経験豊富な東京都登録の耐震診断技術者(建築士)が責任を持って耐震診断を行なっております。
また、創業より60余年木造住宅を造り続けてきた工務店の高い技術力・施工力で、精度の高い、補強工事も行なっております。
アフターメンテナンスを欠かさず、社員や協力会社と共に、お客様のご家族と住まいを長期にわたり見守り続けます。
ぜひ安心して相談ください。