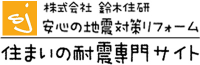耐震コラム
木造住宅の耐震工事と固定資産税の関係とは?
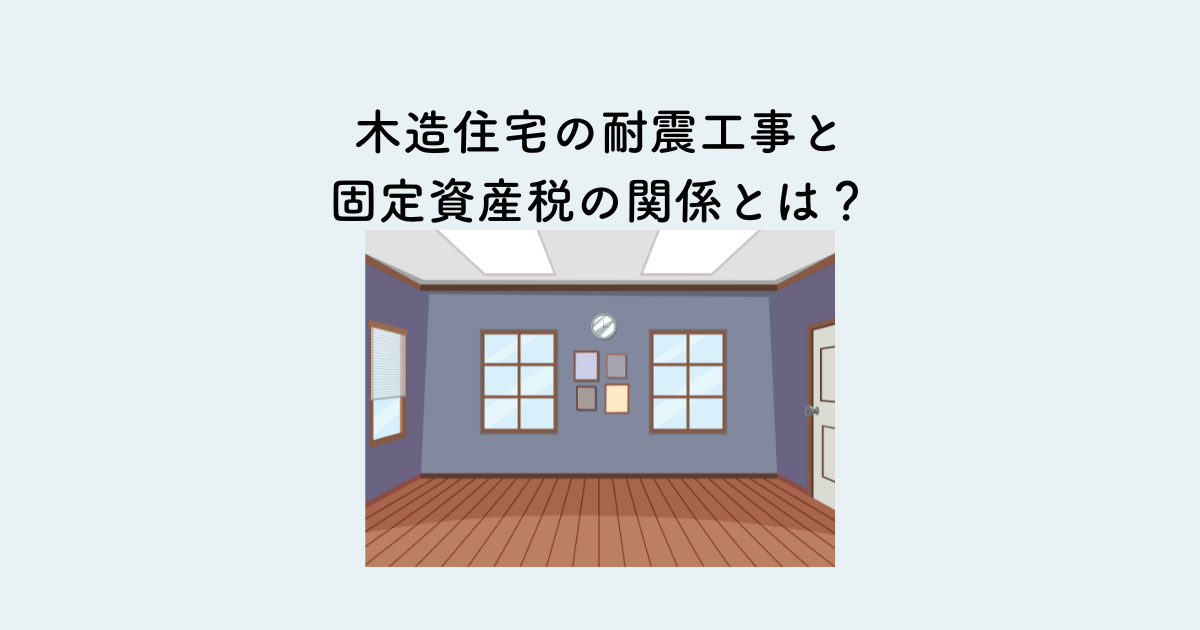
耐震工事は、大切な家を守るための重要な工事です。
しかし、工事後の固定資産税はどうなるのか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
耐震工事と固定資産税の関係性について、特に減税措置の活用可能性に焦点を当てて解説します。
今回は、木造住宅を対象に、分かりやすくご紹介します。
耐震工事と固定資産税の関係性
耐震工事による固定資産税の増減
耐震工事によって固定資産税が増加することはほとんどありません。
むしろ、減額される可能性があります。
固定資産税は、建物の評価額に基づいて算出されます。
耐震工事は建物の構造を強化しますが、必ずしも評価額が上昇するとは限りません。
部分的な補強工事であれば、評価額への影響は少ないでしょう。
ただし、大規模なリフォーム、例えば基礎部分以外を全面的に改修するスケルトンリフォームなどでは、評価額が上昇し、固定資産税が増加する可能性があります。
延床面積が増加した場合も同様です。
固定資産税減額制度の活用条件
耐震リフォームによって固定資産税が減額される制度があります。
この制度は、昭和57年1月1日以前に建てられた木造住宅を対象に、新耐震基準を満たす耐震改修工事を行い、工事費用が50万円を超える場合に適用されます。
減額されるのは、工事完了翌年から最大2年間、固定資産税の半額(床面積120㎡相当分まで)です。
ただし、この制度の適用期限には注意が必要です。
また、減額を受けるには、工事完了後3ヶ月以内に市区町村に申告する必要があります。
耐震工事にかかる費用と減税効果
耐震工事の費用は、建物の規模や工事内容によって大きく異なります。
減税効果は、工事費用と固定資産税の額によって異なります。
工事費用が50万円を超える場合、減税効果は大きくなります。
しかし、減税効果は、固定資産税の額を考慮する必要があります。
具体的には、減税対象となる固定資産税の額を把握し、工事費用と比較することで、費用対効果を検討することが重要です。
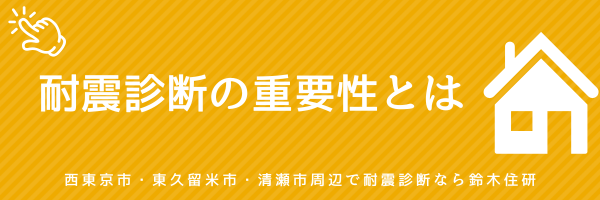
耐震工事と固定資産に関するよくある質問
耐震診断と固定資産税の関係性
耐震診断は、建物の耐震性を評価するものであり、固定資産税の算定に直接影響を与えるものではありません。
しかし、耐震診断の結果に基づいて耐震工事を実施し、減税制度の適用条件を満たすことで、固定資産税の減額を受けることができます。
耐震工事後の固定資産税の申告方法
耐震工事完了後、固定資産税の減額を受けたい場合は、市区町村に申告する必要があります。
必要な書類は、固定資産税減額申告書、住宅耐震改修証明書(または増改築等工事証明書)、工事費用が確認できる書類などです。
具体的な書類や申告方法は、お住まいの市区町村にご確認ください。
耐震工事と固定資産税減額制度の適用期限
耐震リフォームによる固定資産税減額制度には適用期限があります。
適用期限は、自治体によって異なる場合がありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
まとめ
耐震工事は、建物の寿命を延ばし、資産価値を維持・向上させる効果があります。
また、適切な耐震工事を行うことで、固定資産税の減額措置を受けることも可能です。
工事を行う前に、お住まいの市区町村の減税制度について確認し、費用対効果を検討することが重要です。
耐震診断の結果や工事内容、費用などを考慮し、最適な耐震対策と減税制度の活用を検討しましょう。
減税制度の適用条件や申告方法、適用期限については、お住まいの市区町村の税務課などに直接お問い合わせください。
不明な点があれば、専門家への相談も有効です。
当社では、木造住宅の耐震診断・補強を承っております。
また、耐震の減税・助成金制度についての申請・手続きもお任せください。あなたに代わって代行します。
西東京市・小平市・東久留米市周辺で木造住宅の耐震診断でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
無料耐震診断実施中です。
自治体によっては助成金を利用した補強工事にも対応します。
投稿者プロフィール
-
「鈴木住研」では、これまでに300棟以上の木造住宅の耐震診断を行ってきました。
経験豊富な東京都登録の耐震診断技術者(建築士)が責任を持って耐震診断を行なっております。
また、創業より60余年木造住宅を造り続けてきた工務店の高い技術力・施工力で、精度の高い、補強工事も行なっております。
アフターメンテナンスを欠かさず、社員や協力会社と共に、お客様のご家族と住まいを長期にわたり見守り続けます。
ぜひ安心して相談ください。